ときはバブル崩壊前夜の平成2年目、1990年。
岐阜県東美濃市から上京した18才の楡野鈴愛は、憧れの漫画家・秋風羽織に弟子入りを果たします。
彼女の新居となったのは、バブルの華ともいえる12億円のビル……ではなく、その側にある小さな木造アパート。
一人暮らしで心細い、初めての夜に、早速、部屋の天井から、奇妙な音が聞こえてきます。
もしかしてポルターガイストとか!?
もくじ
めっちゃ怖い、ポルターガイスト
ふと思い出したのですが。
おそらく鈴愛らも見て震え上がったと思われる、スピルバーグの映画『ポルターガイスト』という作品がありまして。
出演者が不幸に見舞われた、呪われた映画としても有名でした。
世代的には、それを思い出してゾッとするのもありえるんじゃないですかね。
まあ、たぶん今回はネズミだったみたいですけど。
翌朝鈴愛は、菱本から指導を受けながら、あの広いリラクゼーションルームの掃除をしています。
鈴愛のドジっ子ぶりを知っていると、見ている方はハラハラ。

ここで鈴愛は、左耳が聞こえないことを秋風先生に伝えたいんです、と言い出します。そのことが原因で就職試験に落ちたかもしれないと、気にしていたのです。
「あら、そういえばうちは健康診断がないし」
漫画家やクリエイターさんの落とし穴はそこだったりしますね。
鈴愛は羽織に伝えたいのですが、羽織以下締め切り明けのアシスタントたちも、床で屍のように寝ているのでした。
原稿があがればどうだっていい
菱本に起こされても、羽織はいまだに鈴愛が認識できていません。
【五平餅】と言わないとわからないようです。
「ああ、あのコーヒーぶちまけた。原稿があがればどうだっていいんです。寝ます」
羽織はそう言って、プライベートルームへ。
校了明けは、まさしく「原稿があがればどうだっていい!」という開放感があり、アシスタントたちも自分の場所で眠るため、出て行くのでした。
鈴愛は、菱本に指導されながら、ペン先やカップを洗っています。
換気に、お掃除。ここでアシスタントの紹介です。
若手のボクテとユウコ。
ベテランの中野と野方。
中野はデビュー済みながら、本業がイマイチなのでアシスタントを掛け持ちしないといけないのだとか。
野方はフリーアシスタントとのことです。
「耳が聞こえないからなんだ? 甘えるな」
鈴愛は料理を始めますが、視聴者の想像通りあまりうまくありません。
菱本は、漫画家志願者は手先が器用だから大丈夫、と励まします。
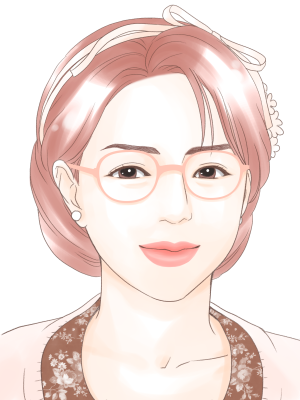
鈴愛はこうして「メシアシ=食事も作るアシスタント」になったわけです。
この業務は幅広く、敷地内のペット墓地にある羽織の愛犬3匹と兎1羽のお供えとお祈りも欠かさずせねばならないとか。
そんなに大事なペットなら自分でお参りした方がいいんじゃない、というツッコミは野暮ですね。
リラクゼーションルームにあった巨匠の絵は、ペットたちの肖像画なんだそうですよ。
そんな羽織は、ボクテとユウコに指導中。
原稿を、裏から透かして見てみるとデッサンの狂いがわかります、とレクチャーしています。
現在のデジタル環境ならば回転ツールかな。
そこで菱本が、楡野さんがお話がありますと切り出しました。
またコーヒー事件か?と勘違いしている羽織に、鈴愛は切り出します。
「私は、左の耳が聞こえません」
「だから何だ? だからといって人とちがう世界が見えるとか、オリジナルの作品が描けるとか? そういうことに頼るな! 甘えるな! 要は想像力、想像の翼は、どこまでも高く広がる!」
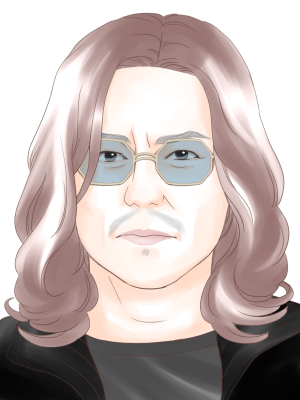
呆然とする鈴愛。
今まで左耳の失聴をハンデと見なされたことはあっても、個性と思われることはなかったからです。
ホントの火事を知りたくてアパートを燃やそうとする
「気にしないで、ああいう人だから」
ボクテがそう話しかけてきます。

鈴愛たちの住むアシスタントの家が少しきな臭いのは、火事の場面を描くため、少し燃やしたのが原因だとも。
火事の場面を描くためには家を買って燃やそうとする(消防署に止められたそうですけど)。
それが秋風羽織!
「先生にとっては作品がすべてなんだ。だからぼくのことでも。ほら、ぼくってゲイじゃない?」
このセリフで、ボクテも性的嗜好のせいでいろいろ嫌な目にあってきたことが示されていると思います。
鈴愛は興奮して母に電話します。
当時、東京から岐阜に電話すると、7秒10円かかったのです。鈴愛は10円玉を大量に用意したのでしょう。テレホンカードが欲しいところです。
鈴愛は興奮している上に無茶苦茶な話し方ですが、左耳をハンデではなく個性とみなされたことが嬉しくて仕方ないようです。
「ゲイもおる! テレビや物語でしか会うことのないゲイ!」
という、この無神経にも思えるセリフが、当時のリアルです。
さんざんテレビやメディアでお笑い扱いされてきた当事者がそう名乗りでることができるはずもないわけです。
鈴愛の、現代からすればデリカシーのない言葉は、当時のリアルです。
ここでは描くもの、作るものが全て。
そう興奮する鈴愛に対し、晴は就職試験のことを気にしとったのか、と問いかけます。
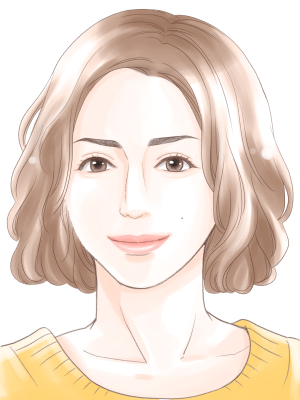
電話が切れてしまってあわてる鈴愛の背後を、ユウコがふふっと笑って通り過ぎます。
「おかあちゃん」という呼び方のせいかな、と思う鈴愛でした。
律が遊び呆けないよう鈴愛が重石に
1週間後、律も上京してきました。
自分だけの電話もつきました。
留守番電話はあるけど、コードレスではない、そんな当時最先端機能の電話機です。

律の部屋はモノクロ中心のインテリアでまとめていて、なかなかおしゃれ。
バブル時代のおぼっちゃま大学生の部屋らしさが感じられます。
羽織のオフィスや律の部屋の洗練。ふくろう町や鈴愛のアパートのようなレトロ。
それが同時に存在するのがこの時代です。
引っ越しの手伝いに来ていた和子は、鈴愛と近所にした、と言います。
「なんで? ここは新宿区で、あいつは港区でしょ? またあいつと一緒なの?」
割と近いみたいですよ、律くん。
西北大学(早稲田想定)に通う普通家庭の学生さんだと、家賃の安い西武新宿線沿いが最も多いそうですが、港区に近いとなると四谷三丁目辺りかな。
実は住むところも結構あって、しかも十分に通学圏内。こういうところもキッチリ辻褄を合わせてる気がします(前作『わろてんか』は地理関係も破綻気味)。
和子はここでこう指摘します。
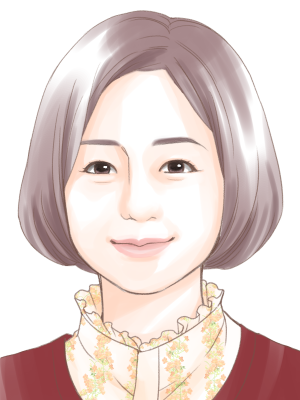
母として見抜いた性格として、律は岐阜県民であることをやめ、東京で遊ぼうとしていると。
「鈴愛ちゃんには、その重石となってもらいます!」
和子はキッパリ。
やっぱり二人は運命の仲なのかな?
今日のマトメ「冷たいようで、かえってそこがよい」
ノスタルジックな昨日までとは変わって、今日からは鈴愛が新環境に馴染もうとします。
本作でホッとしたのは、変人の羽織も、宇太郎と容赦ない口論をした菱本も、鈴愛に対して理不尽なダメ出しはしないところです。
料理が苦手だと鈴愛が言っても、手先が器用だから大丈夫だとフォローする菱本。
優しいボクテはもちろん、羽織もコーヒーの件では特に鈴愛をねちっこく責めたりしません。
クセがある性格であっても、目下の人をネチネチといびってストレスを解消するような、そういうところはないようです。
そういう「嫁いびり」「新人いびり」系のダメ出しは、朝ドラではあんまり見たくないんですよね(NHK大阪は好きみたいですけど)。
とっつきにくくてマイペースだけど、あまり踏み込まない。
東京に出てきて、自分の腕前だけで生きていく人々。
人情味あふれるふくろう町とは違った、サバサバしているからこその人間関係の良さがあると思います。
岐阜での人間関係は、左耳のことを気遣うか、遠ざけるか。
あたたかいようで、冷たい部分があって、そこに鈴愛は傷ついていました。
東京で新たに見出した人間関係は、左耳のことを無関心なようでいて、ハンデとはみなさない。
冷たいようで、かえってそこがよい。
そう鈴愛は感じたのでしょう。
新たな世界に、鈴愛が心地よさを感じ始めています。
著:武者震之助
絵:小久ヒロ
【参考】
NHK公式サイト

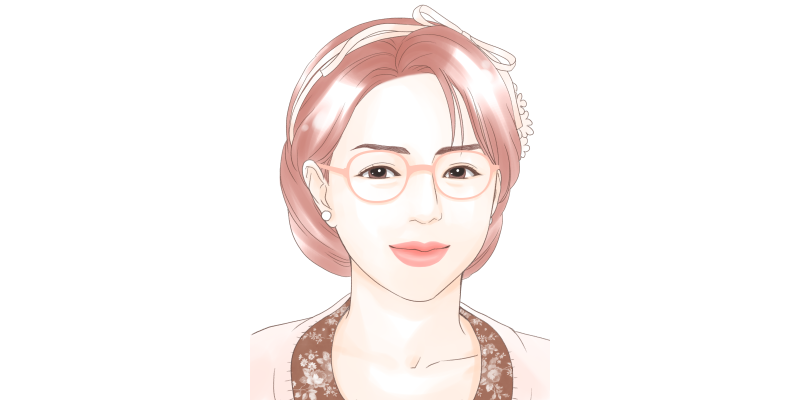


「だから何だ? だからといって人と違う世界が見えるとか、オリジナルの作品が描けるとか? そういうことに頼るな! 甘えるな! 要は想像力、想像力の翼はどこまでも広がる!」
この台詞の前の鈴愛の台詞を「私は著名脚本家です」に置き換えると、
『わろてんか』や『西郷どん』にピッタリはまってしまいますね。
両作品の脚本家氏、聞こえてるか?