昭和59年(1984年)の正月――。
もう若くもない八郎は、腰に痛みを感じつつ、武志が羽付きをしております。相手は大野家の桜と桃姉妹です。
姉妹が笑い、お礼を言い、百合子がこう告げる。
「帰るでえ。はい、お礼いうてぇ」
「お年玉ありがとうございました!」
「ありがとうございました!」
そう告げる従妹たちに、武志はこう返す。
「来年は負けへんで!」
なんちゅう顔してんねん。ほんまや、どういう顔してんねん。墨を書かれた顔をみあわせ、父子は笑う。
喜美子もたまらず笑い出す。
何もない、平凡な、それでいてあと何度あるかわからない。そんな正月がそこにはあります。
目標を百個持つこと
喜美子は、おせち料理を詰めています。
本作はいつもこういう料理がおいしそう。たまらないものがあります。
武志は、お父ちゃんに県立病院へ行ったことを伝えてない模様。心配をかけたくないのですね。
喜美子がここで宣言します。
「お母ちゃんな、車の免許取ろう思うねん。今年の目標や。百個あるうちの一個や。免許あると便利やろ。車いいやろ」
武志はそもそも車がないと困惑していますが、喜美子は「買うで!」と即答します。
「本気やな」
「車欲しい思わへん?」
「そらあったら便利やけどな。でもお母ちゃんが免許とれるやろか?」
「がんばって取るよ」
「誰を乗せるん?」
「雨の日とかな。武志のこと送ってやれるわ」
案の定、堂々として力強い喜美子なのです。ヨヨヨと泣くとか。アルカイックスマイルとか。そういうことでなくて、ええアルトで胸を張って宣言する。
根底にあるのは愛。
抵抗力が低下してゆく我が子を送るため。県立病院まで通院するため。そういう深い愛がある。
喜美子はいつだって愛に溢れている。その出し方が、ちょっと普通の女とは違うだけです。
「武志はなんなん? 今年の目標? 百個作りぃ。目標はいっぱい作っとけぇ」
そう元気よく言いながら、喜美子は思い出してしまう。大崎の言葉を。
僕は患者さんに、本当のことを伝えたいと思っています。病名の告知をするということです――。
いつ、告げるのか?
喜美子は悩みを抱えているのでした。
ろくろに向かうそれぞれの姿
ろくろに向かう武志。その様子を八郎が見ています。
「あ〜!」
ここで失敗してしまう。惜しいなあ、惜しいことないわ。そう言い合いながら、お父ちゃんやってやと甘えます。
武志がやらな勉強にならんやろ。そう当惑する八郎。ここへ喜美子がお茶を持って入ってきます。
「なあ、お母ちゃんな、今年の目標百個あんねんて」
「言わんでええ、いちいち言わんでええてもう」
喜美子はぶっきらぼうにそう言います。八郎は、我が子を気遣っています。
窯業研究所修了後はどうするのか?
この三月で修了のため、掛井先生に相談したところ【素地焼き】を勧められたとのこと。
同じものを素早く作る。今の感じやったらまだまだやで、毎日ろくろの前に座りぃ。そう八郎が語るわけですが、劇中では喜美子の姿の方が多かったようにも思えます。
「ここきたらええやん!」
その喜美子はそう勧める。いっそのことアパートを引き払うても戻ればええ。家賃いらん。
そう言うのですが、病名を伏せている今はまだ本音を明かせず、八郎もそれはどうかと突っ込む。武志はご飯も一人で作れるし、洗濯物も畳める。これが結構うまい。たこ焼きには紅生姜を入れすぎやけど……と聞いて、喜美子は驚きます。
八郎がアパートに行ったんかい! 聞けば信作叔父さんと来たそうで。
男はええと武志が言うと、喜美子は今度絶対行ったるからなと力強く宣言するのです。女性立ち入り禁止。そう言われると、喜美子は力強く返す。
「あいにくお母ちゃんは女性やない。お母ちゃんは、お母ちゃんいう生き物や」
さりげないようで、本作の本質に迫るセリフだとは思いました。
本作でしつこく叩かれるのは、喜美子の女性的ではないところでして。
声が低い。下品。やりすぎ。狂気。生意気。化物。
褒められるにせよ「兄貴」というような男性的な言われ方がされる。
でもこれって【変成男子(へんじょうなんし・女子は成仏が難しいからいったん男子になるという仏教の思想)】をスルッと、無自覚でしていることかもしれないわけですよ。女性ってこういうことされますよね。
なんでや?
女のままではかっこよくなれんのか?
といいつつ、私も菅原文太さんや織田信長にたとえておりますけれども。
やはりこれまでは、かっこいいのは男の特権だという意識はあった。
喜美子は、デナーリスあたりと一緒にそこをぶちぬく、新機軸の存在です。
喜美子は喜美子や!
ものに宿る時間と人生
ここで八郎が鹿路に向かおうかと言い出す。武志は見たことがないと言い出す。覚えてへん。記憶にあるのは喜美子の姿でした。
「ほや、お母ちゃんがここに座って、なんや作っててん。それをな、ずーっとここで待っててん。あれなんやったっけ?」
そんなこともあった。武志がすぐ破る靴下をつくろうことで、お小遣いをあげていた。そんな日々です。
お母ちゃんはずるい。お母ちゃん、武志のことどう思うているか言うてきて。
「好きちゃうわ、大好きや!」
そう言うてきた。あのときを思い出しているのです。笑いつつも、喜美子だけは複雑な表情を少し見せています。流して見られない朝ドラです。
八郎はここで、意を決したようにろくろの前に座ります。
腕まくりをして、足でスイッチを入れる。
「おお……はぁ、流石やなあ。ずっとやってへんいうたのに」
久しぶりやで、ほんまに。手ぇが覚えてんな。すごいな。うまいなあ。武志に褒められて、八郎はうれしそうではあります。子どものくせにと威張ることはしない。しみじみと喜びを噛み締めているのです。
「ほやけど、お母ちゃんのとはまたちょっと違う」
武志はそう言います。人によって癖いうもんがあるからな。そうキッパリ言われるのです。
八郎から、喜美子へ。喜美子から、武志へ。
そのことを理解しつつある、そんな武志でしょう。
かつて彼は、穴窯のことをあっさりと元弟子に伝えた母に疑念を感じておりました。癖があるからには、同じものにはならない。そういうものはあるはず。
男であり上にいる。そういう八郎を、妻という下にいるはずの喜美子が乗り越えたように思えること。そういう偏見があればこそ、二人はつらい目にあったはず。
違いを上下ではなく個性だと思うことができれば、そんな偏見に苦しめられないで済むのでしょうに。
そうやって、夫婦でも、親子でも、別人格で切り分けるところが好きだと思った。
主人公の凄さを強調するためか、過剰なまでに親を意識する子というのは、好きになれないんです。親が当たり前のように、我が子ならこの気持ちがわかるだろうと押し付ける。そういう世界も、勘弁していただきたい。
誰もが別人格で、協力はするけれども、区別をつけている。そういうところが本作にはあると思う。
「共依存」とか、ベタベタしすぎとか。そんな意見も本作にはありますが、くっついて、離れる。そういう距離感の取り方を模索しているように私には思えます。
※続きは【次のページへ】をclick!

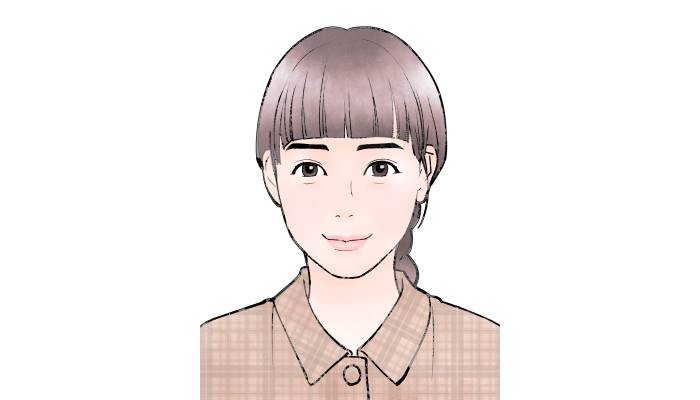
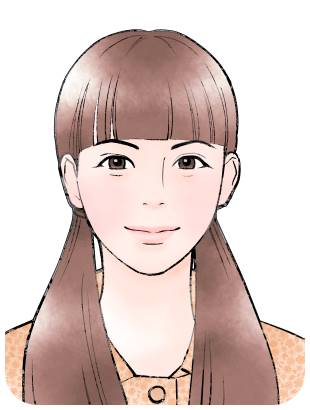







コメントを残す