琵琶湖を前にして、直子と信作が叫んでいます。
「海やぁ〜!」
「海やでぇ〜!」
喜美子は腕組みして、彼らを見ている。そしてこう言うのです。
「武志」
「おう」
「日本一の湖や。よう見とけえ、こっちの心も大きなるで」
この言葉は、第一回の冒頭でジョーが喜美子たちに語ったものと同じです。
喜美子は明確に、性を超越して、母と父を兼ねるような存在になっているのだと思います。
「皆さん一緒に写真とりましょ」
大輔がそう言い、シャッターを切ります。
親世代の親友三人、子世代の親友三人とその妻。そして川原三姉妹。大切な人たちの、特別な一枚がこうして撮影されたのです。
ぎゅ〜、幸せやなぁ
四月、武志は桜と桃と約束したピアノの発表会を見に行く約束を果たしました。“彼女”こと真奈も一緒に行ったようです。
そして彼と喜美子は、陶器に向き合う日々を過ごしてゆきます。
自分の作品に対して、真剣に向き合う二人。この二人が陶芸に向き合うだけで絵になる。ストイックなまでに削ぎ落とした本作の美学を感じます。
武志は手を洗い、「おーっほほっ、すごいな!」と喜美子の作品を見ています。
喜美子も、ここで手を洗いました。そして立ち上がり、武志にこう力強く宣言します。
「ぎゅ〜したろか。ぎゅ〜したる」
「えっ?」
「ぎゅ〜してええ?」
「お母ちゃん……」
「うん?」
「ええに決まってるやん」
「ほな」
喜美子はやはり、最終回まで喜美子やな。信作との初対面で「よっ!」と挨拶していた頃から、本質は変わらない。突拍子ないし、距離感いきなり縮めるし、堂々と宣言する。こういうところがずっとあったなぁ。
でも、いきなりではなくて許可を取るあたりも、喜美子らしい。八郎と呼び方で悶々としていました。決めるなら決めぇ! そう言い切る強さがずっとありました。
ほんまに、最後まで、喜美子は喜美子で……。
武志はここで慌てています。
「あっ、ちょっと待って、嘘や、うそや、うそや、いやもう歳やし恥ずかしい!」
「ええ言うたやん」
喜美子は照れる我が子をぎゅ〜します。好きやのうて大好き。そんな抱擁です。
「ぎゅ〜!」
「うわ〜苦しい!」
「はははっ!」
「いやもうわかったて」
「あはははは」
笑いながら抱きしめる。この一瞬が幸せでたまらない。そんな境地がそこにはあります。
「幸せや!」
「えっ?」
「幸せやで!」
「幸せか」
「幸せや!」
「幸せやなぁ」
「ありがとう!」
「なになになに?」
「ぎゅ〜!」
「なんで! もう苦しいってもう!」
「幸せやなぁ、武志」
「幸せやー」
ぎゅう〜。喜美子は我が子を抱きしめ、幸せを噛み締めています。
「いや無理無理無理!」
「おなら出せやぁ!」
「おなら出るてほんまに! 苦しいて!」
母に抱きしめられて、子はそう笑っています。
悲壮感が一切ない場面で。病気なんか関係ないようで。でも、病気を知っていて、余命が短いからこそ、この一瞬を確認するような抱擁で。
普通が特別なこと。そんな瞬間を切り取ったような、切なく、美しい場面でした。
大崎のクールな皿を作る
そして二年後、武志は、26歳の誕生日を前にして旅立ちました――。
そう語られます。
視聴者の目に焼き付いた武志の最後の姿は、母に抱きしめられるものとなったのでした。
桜の季節、大崎が「かわはら工房」を訪れます。
喜美子から武志の作品を「手にとって見てやってください」と促され、大崎はしみじみと眺めています。
「わあ……綺麗ですね」
武志は作品を残しました。武志の作品は生きています――。
そうナレーションが語ります。
稲垣吾郎さんは役者として、鏡になりました。自分の演技を押してゆくのではなく、作品そのものの素晴らしさを写す鏡として、そこに存在しています。誠意ある演技です。そんな鏡のような大崎だからこそ、武志の作品が放つ生命の輝きが見えるようです。
「先生のクールいうイメージですけど。こういうのはどうや思うんですけどね。うちがこのお皿を入れますんで、出してそれをかけてくだい」
大崎へのお礼の皿が気になっていました。ここで作るようです。
「あ、いや、よく意味がわからないんですけど」
お互いコミニケーションエラーが発生しとります。喜美子も大雑把だし、大崎もふわっと理解していて、噛み合っておりません。喜美子は釉薬が入っている、それを模様にすると説明して、やっと大崎は「ああ、そういうことなんだ」と理解します。
緊張しつつ、先生のクールなイメージを釉薬で表現しようとする大崎。ここで「ちょっと待って」とある話を切り出します。
亡くなる三日前に握手をしたんです。
集中治療室で……目を少ーし開けた時があって、手をこういう感じで、大丈夫だよって握ってあげたら、握り返してくれたんです。
意外にも力強くて、こっちも両手で武志の手を握り返して、握手したんです――。
陶器と向きあい、作り続けてきた武志の手。それを握り返した大崎でした。
大崎に武志を救って欲しいという声は、ずっとありました。
救えなかったようで、実は救ったのだとは思います。最期に向かう中で、こんな誠実な医師がいることは、それはそれで幸せなのです。
これを聞いた喜美子と大崎は軽く笑いあいます。そして喜美子はこう言います。
「じゃあ始めましょうか」
「お願いします」
「よーし、ほな行くでぇ!」
不器用に釉薬をかける大崎。大崎は、仕事関係ではしっかりしているのに、それ以外がマイペースなところに彼らしさがあります。
「ほんで振ります振ります、ええやんええやん!」
「えっ、合ってますか、こうですか?」
こうしてできてゆく、クールな大崎先生の皿。その完成品は、各自ご想像ください。
陶芸家・十代田八郎の挑戦は続く
夏が過ぎ、秋になりました。紅葉が赤くなる中、喜美子は一人で食事を終えています。
そこへ八郎が「おう」とやって来ます。
「何食べた?」
「たぬきそば」
「おう、ええな」
そう語りあい、縁側で蜜柑を剥きつつ話し合う。
そういえば穴窯の前にも、夫婦でこうして蜜柑を食べたとき、お互いの剥き方の癖を知らなくて驚いていましたっけ。【普通】が夫婦でも違うことが浮き彫りにされました。
八郎は、今後の見通しを語ります。長崎に移り、江戸時代の「卵殻手(らんかくで)」という陶器に挑戦するそうです。
「名古屋を引き払うて、今度は長崎や」
そう言い切るのです。どうせ名古屋を引き払うのであれば、「信楽に来て喜美子と暮らせばええのに……」という思いを抱く方は多いかとは思います。そういうコメントもありましたもんね。
ただ、再挑戦とは、彼が幼い頃から敬愛していた深野先生と同じ道ではあります。
喜美子への思いも、武志に寄り添う気持ちも。彼の進路を変えてはいない。思えばあの三津も、離婚のきっかけになっただけでした。
陶芸へ向かう彼自身の心と思いが、人生を変えてゆきます。これも本作の罠、わかりにくさではあります。
離婚の原因にせよ、まだわからないという意見がある。ドラマが終わってやっと、製作側からの回答は示されました。
根底にあったのは、喜美子ではなく八郎の【嫉妬】でした。性欲や恋愛感情が絡んだわけではありません。
女偏がつくだけに【嫉妬】は女の感情とされがち。これは生物学的なものというよりも、社会がそういう結び付け方をして来たのです。このレビューでも突っ込んだ“女優同士のドロドロ報道”も、そうした感情の反映です。
こういう女同士が争うことを見たい欲求は、典型的な【ミソジニー】(女性嫌悪)の発露とされております。
そして、そんな先入観に支配されていると「女ではない男の【嫉妬】てなんやねん? DVや浮気もないのに離婚なんてありえへんで!」と理解ができず、ずーっとぐるぐるそこで回ることになる。尻尾を追いかけて回る犬みたいなもんやな。
ともかく八郎の【嫉妬】が煮詰まっていた頃から、様々な出来事と時間を経てからの、縁側での蜜柑です。
喜美子はここで、自分の反省点を吐き出します。
「あんな……」
「うん?」
「うち、武志に、死なさへん言うてしもた。絶対死なさへん。お母さんが生かしたる言うた。エゴやな。うちの悪いとこや。なんとかしたかった。なんとかしてやりたい思うてた。そんなん無理やのにな」
そんなん喜美子のせいやない……と言いたいところですが、そういうコメントが既にあるようです。
※続きは【次のページへ】をclick!

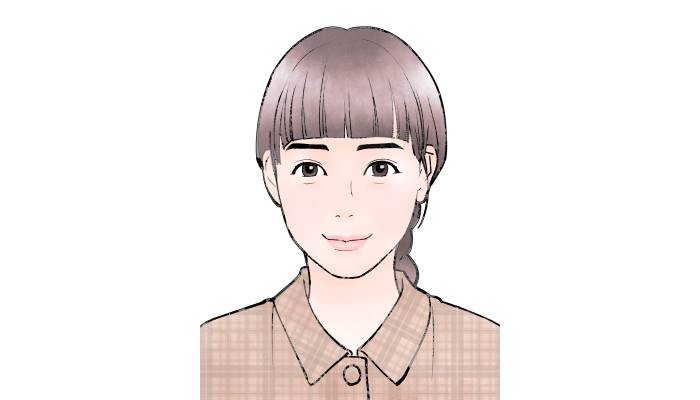









コメントを残す